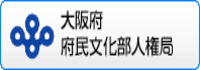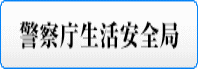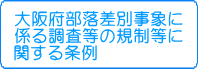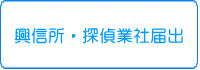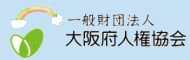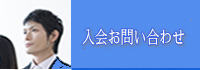一般社団法人 大阪府調査業協会は探偵・興信所。調査に関することなら何でも、私達、探偵・興信所のプロ集団に。
TEL. 06-6867-7657
〒542-0081 大阪市中央区南船場3-1-16
調査業者のガイドラインGUIDELINES
調査業者のガイドライン
「調査業者のガイドライン(指針)」
協会調査業者のガイドライン(指針)
社団法人大阪府調査業協会
1 基本理念現在の高度情報化社会では、情報のもつ価値が飛躍的に高まっており、膨大な情報のなかから必要な情報を収集するため、調査活動の果たす役割は一層重要になっている。
こうしたなかで、あらゆる企業の活動や個人の生活上においても、今までにも増して、安心して相談し、依頼のできる「信頼のおける調査業者」の必要性が強く求められている。また一方で、「人権」が、国際的なキーワードになっているように、人権の尊重が平和の基礎であるということが共通認識になりつつある。そこで、調査業が、信頼ある調査のプロとして、調査目的や手段の正当性を確保しながら、人権問題にも配慮した調査活動を行っていくためのガイドライン(指針)を策定する。2
3 4 ガイドラインの目的このガイドラインは、調査業者が、今後の調査業活動を行っていくうえでのよりどころとなるものである。
部落差別調査等規制等条例の趣旨の徹底と依頼者への啓発平成10年に発覚した、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(以下「条例」という。)違反の差別調査事件を教訓|と
して、調査業者は、条例で禁止されている次のような調査を行わないことについて改めて徹底を図るとともに、依頼者に対しても、部落差別調査の発生防止のため必要な啓発に努める。
(1)特 定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が同和地区にあるかないかにういて調査し、又は報告しない。(2)同 和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしない。
適正な営業活動の確保
(1)広 告、勧誘等の営業活動にあたっては、適正な内容を表示する。
(2)調 査の受件にあたっては、書面により、調査の内容、報告の形式、調査にかかる費用等の契約内容を顧客との間で相互に明確にするなど、消費者保護に1^分配慮する。
7 人権尊重に配慮した調査活動の実施
(1)依 頼者の調査目的を確認し、違法な調査や不当な人権侵害につながる調査は受けない。
(2)合 法的な手段による適正な調査活動を行う。
(3)採 用調査にあたっては、企業が採用応募者の適性・能力に応じた公正な採用選考を行う社会的責任を有していることに留意し、調査対象者の人権の不当な侵害にならないよう、調査目的に応じた必要最小限の情報を収集し、報告するなど、とくに慎重な取り扱いに努める。
(4)結 婚調査にあたっては、調査対象者の人権の不当な侵害にならないよう、とくに留意し、調査、報告を行う。
(5)情 報の収集、管理にあたっては、調査対象者の個人情報の保護に十分配慮する。とりわけ、思想、信仰、信条、その他の心身に関する基本的な個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、調査目的に照らして、不当な人権侵害にならないよう、よリー層留意し、とくに慎重に取り扱う。
(6)誤 った情報によって権利利益の侵害が発生しないよう、報告内容の正確性の確保に最善を尽くす。
人権意識向上への取り組み
(1)調 査業は、人権問題に密接に関わっていることを認識し、受件、調査、報告の全過程を通じて、調査対象者の人権の尊重に配慮するとともに、自らの人権意識の向上に努める。
(2)こ のガイドラインに示す人権尊重の精神を遵守した調査活動が実施されるよう、従業者に対しても適正な指導及び監督に努める。業界全体の発展と社会への貢献条例を連守し、自ら適正な調査活動を行うとともに、行政との連携のもとに、人権尊重を基本とする健全な業者の育成に努めるなど、信頼される調査業の構築に努め、人権が尊重される社会の実現に向けて貢献する調査業をめざす。
1 基本理念現在の高度情報化社会では、情報のもつ価値が飛躍的に高まっており、膨大な情報のなかから必要な情報を収集するため、調査活動の果たす役割は一層重要になっている。こうしたなかで、あらゆる企業の活動や、個人の生活Lにおいても、今までにも増して、安心して相談し、依頼できる「信頼のおける調査業者」の必要性が強く求められている。また、一方で「人権」が、国際的なキーワードになっているように、人権の尊重が平和の基礎であるということが共通認識になりつつある。そこで、調査業が、信頼ある調査のプロとして、調査目的や手段の正当性を確保しながら、人権問題にも配慮した調査活動を行っていくためのガイドライン(指針)を策定する。
【趣 旨】このガイドラインを制定するにあたっての基本理念を宣言したものです。
【説 明】平成8年5月 に国の地域改善対策協議会(会長宮崎繁樹)から出された「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」の意見具申の中で、人類は、今世紀の二度にわたる世界大戦の惨禍や多発する各地の地域紛争のなかで、平和のないところに人権は存在し得ない、人権のないところに平和は存在し得ないという大きな教訓を得、今や人権の尊重が平和の基礎であることが世界の共通認識となりつつあり、このような意味において、21世紀は「人権の世紀」と呼ぶことができるとしています。また、国連においても、1995年からの10年間を「人権教育のための国連10年Jと し、世界中で人権教育を推進する取り組みが進められています。このように「人権」や「人権教育」が国際的なキーワードとなりつつあります。
大阪府では、昭和50年末の部落地名総鑑事件を受けて、昭和60年に「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」(以下「条例Jといいます。)が市1定されました。この条例では、部落差別事象につながる調査報告を規制しています。これ以降、社団法人大阪府調査業協会(以下「協会Jといいます。)をはじめ、府内の調査業者は、部落差別をなくすための自主規制に努めてきました。しかし、大阪府内では、平成9年3月の条例違反事件に引き続き、平成10年6月に発覚した大規模な条例違反事件など、調査業界全体の信用を失墜させるような事件が起こっています。
協会は、今後調査業の進むべき方向、業界のあり方を検討するため、平成9年に各界の有識者からなる運営審議会を設置し、「調査業者及び協会の今後のあり方〜調査業は、今後人権問題にどのように配慮していけばよいか、及び調査業界のレベル向上の方策について」諮問し、翌年6月に答申を得ました。このたび、協会は、その答申をうけて、調査業者の今後の行動指針となるガイドラインを作成しました。このガイドラインを社会に示し、業界の人権問題に対する意識や姿勢を明確に示し、実践していくことが、調査業に対する信頼を高め、よリー層の社会的地位の向上が可能になる道と考えています。来る21世紀に向けて、調査業界が一体となって人権尊重に向かって進んでいきたいと考えます。
2 ガイドラインの目的このガイドラインは、調査業者が、今後の調査業活動を行っていくうえでのよりどころとなるものである。
【趣 旨】このガイドライン(指針)は、調査業者が、今後の調査業活動を行って行くうえでのよりどころとなるものとして作成したものです。
【説 明】このガイドラインには、今後の調査業者のあるべき姿を念頭におき、さまざまな観点からの行動指針となっています。我々調査業者は、このガイドラインを遵守した事業活動を行うことを表明し、実践していくことが、社会の信頼を得ることにつながると考えます。
3 部落差別調査等規制等条例の趣旨の徹底と依頼者への啓発平成10年に発覚した、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例(以下「条例」という。)違反の差別調査事件を教訓として、調査業者は、条例で禁止されている次のような調査を行わないことについて改めて徹底を図るとともに、依頼者に対しても、部落差別調査の発生防止のため必要な啓発に努める。
(1)特 定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しない。(2)同 和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしない。
【趣 旨】平成10年に発覚した部落差別調査事件を踏まえて、条例の趣旨を再確認し、業界に再度徹底するとともに、調査の依頼者に対しても、必要に応じて、啓発に努め、部落差別事象を撤廃し、同和問題の解決に積極的に貢献していこうとする、調査業者の明確な姿勢を示すものです。
【説 明】条例では、大阪府内の業者に対して、次の2つの事項を規制しています。
(1)特 定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、報告しないこと。これは、「居住地が同和地区にあるかないかについて」の調査や「居住地が同和地区にある又はない」ということの報告行為をしないということです。また、報告した内容の真偽に関わらず、部落差別事象を引き起こすおそれのあることは明らかですので、同和地区にある又はないという報告を行えば、この事項に該当します。なお、「同和地区」という表現だけでなく、「被差別部落」等の同義の表現を用いた調査行為、報告行為も該当します。
(2)同 和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
これは、(1)に関連して、いわゆる部落地名総鑑の発行などの同和地区の所在を明らかにする行為に関して定めたものです。つまり、「同和地区の所在地の一覧表等Jの提供及び「特定の場所又は地域が同和地区にあること」の教示をしないということです。これは(1)と 同様に、教示の内容の真偽に関わらず該当します。
さらに、「同和地区Jという表現だけでなく、その同義の表現を用いた教示も、これに該当します。また、「一覧表等」とは、一覧表のほか、同和地区の所在地を明らかにした図書や地図などが含まれます。また、「提供Jとは、「他人が利用しうる状態に置くこと」を言い、具体的には、「販売、賃貸、交換、贈与等Jがあげられます。また、「教示」の方法については、文書、日頭を問いません。また、特定個人が同和地区の出身かどうかといったことは、どのような場合であっても、およそ必要のない情報です。もし、こうした依頼があった場合に、それを引き受けて調査し、報告することは、調査業者が、部落差別につながる人権侵害に加担することになります。私たちの調査の結果、結婚や就職という人生の重要な側面において、基本的人権が侵害される事態を生じさせてはなりません。
また、部落差別につながる調査の依頼があった場合は、自ら受けないのはもちろんですが、依頼者の意識が変わらない限り、依頼者は調査願望を持ち続けることになります。そこで、私たちは、そうした依頼者に対しては、条例の趣旨を十分説明して、意識啓発を行うなど、今後の部落差別事象の発生を防止することに貢献する姿勢を明確にしていきます。
4 適正な営業活動の確保
(1)広 告、勧誘等の営業活動にあたっては、適正な内容を表示する。
(2)調 査の受件にあたっては、書面により、調査の内容、報告の形式、調査にかかる費用等の契約内容を顧客との間で相互に明確にするなど、消費者保護に十分配慮する。
【趣 旨】情報化が一層伸展するなかで、調査業の活動領域がさらに広がることが想定されます。これまで、調査業は、一般消費者からみると、業務内容や存在について十分認識されていない部分があったことは否定できません。調査業が、今後、高度な専門性に支えられた情報サービス業として、よりよいイメージのもと、認知度を高めていくために、消費者保護にも留意し、しっかりとした企業倫-6理を確立し、適正な営業活動を行っていく姿勢を示すものです。
【説 明】
(1)広告、勧誘等の営業活動消費者と私たちの接点の一つとして、電話帳、チラシ等の広告媒体があります。各調査業のセールスポイントを記載することはもちろんですが、その内容に事実に反する表示、誇大な表示、誤解を招くことを意図した表示等があってはなりません。また、料金をめぐるトラブルが生じないように、金額の記載には配慮する必要があります。現在のところ、消費者センター等への調査業に関わる苦情相談は少ないようではあるが、苦情や不満が表面化しないまま、業者全体に対する不信感につながることがあってはなりません。
(2)消 費者保護への配慮現在、消費者契約法(仮称)の法制化など、新しい時代への消費者問題への対応が検討されており、事業者に対する正当な取引行為が強く求められる傾向にあります。こうしたことに対して、調査業も対応していく必要があります。契約にあたっては、契約内容を十分説明し、依頼者と調査業者の合意内容を明確にしておく必要があります。また、その際には、書面により、調査の内容、報告の形式、調査にかかる費用等の契約内容を明確にしておくことが、今後、お互いのトラブルの防止につながります。
5 人権尊重に配慮した調査活動の実施
(1)依 頼者の調査目的を確認し、違法な調査や不当な人権侵害につながる調査は受けない。
(2)合 法的な手段による適正な調査活動を行う。
(3)採 用調査にあたっては、企業が採用応募者の適性・能力に応じた公正な採用選考を行う社会的責任を有していることに留意し、調査対象者の人権の不当な侵害にならないよう、調査目的に応じた必要最小限の情報を収集し、報告するなど、とくに慎重な取り扱いに努める。
(4)結 婚調査にあたっては、調査対象者の人権の不当な侵害にならないよう、とくに留意し、調査、報告を行う。
(5)情 報の収集、管理にあたっては、調査対象者の個人情報の保護に十分配慮する。とりわけ、思想、信仰、信条、その他の心身に関する基本的な個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、調査目的に照らして、不当な人権侵害にならないよう、よリー層留意し、とくに慎重に取り扱う。
(6)誤 った情報によって権利利益の侵害が発生しないよう、報告内容の正確性の確保に最善を尽くす。
【趣 旨】これからの調査業は、人権尊重に配慮した調査活動を行うことが求められており、その具体的な内容を示したものです。
【説 明】
(1)違 法な調査や不当な人権侵害になる調査私たちには、さまざまな調査の依頼がありますが、法令などに反する違法な調査、内容や目的が不当な調査を受けることは、業界の信用の失墜につながります。不当な調査としては、犯罪行為につながる調査、公序良俗に反する結果を招く調査などがあげられます。また、違法な調査や不当な人権侵害につながる調査であるかどうかを判断するにあたっては、依頼者の意図を正確にくみ取ることが必要です。ときには、依頼者が真実を告げないこともあり得ますので、受件にあたっては、依頼者の名前や目的などを正確に確認する必要があります。その上で、依頼者が暴力団関係者など反社会的活動を行う団体の構成員の疑いがある場合や、匿名や電話のみによる依頼、直接の当事者以外の者からの依頼などのように、依頼者の本人確認や依頼内容の確認が困難な場合は、注意を要します。
(2)適 正な調査手法による調査活動窃盗、盗聴や他人の家への無断侵入などの法令に反する方法を用いた違法な調査や不当な方法による調査は行ってはなりません。
(3)採 用調査にあたっての取り扱い採用調査にあたっては、「就職Jという個人の自己実現に関わる重要な問題に関わっていること、また、企業にとっても、応募者の適性・能力に応じて公正な採用選考を行う社会的責任を有していることも十分踏まえなければなりません。したがって、企業からの依頼を受けた調査業者は、集めうる限りの情報を幅広く調査し、報告するというのではなく、目的に応じた必要最小限の情報の収集・報告に努めることにより、調査対象者の人権や利益を不当に侵害することのないよう、特に慎重に取り扱わなければなりません。
(4)結 婚調査にあたっての取り扱い結婚調査も、部落差別調査との関係で問題とされてきました。交際相手が同和地区の人かどうかといった調査は決して許されないものですが、重婚でないなど本当に結婚できる状態にある人かどうかといった、いわば契約行為の前提となる調査もあります。調査業者は、結婚調査について、調査対象者の人権の不当な侵害にならないよう、とくに留意し、調査、報告をしなければなりません。
(5)調 査対象者の個人情報の保護への配慮情報化の伸展のなかで、自分に関する情報がどのように扱われているかを知る、つまり自己に関する情報を自ら実効的にコントロールできるようにしていこうとする大きな流れがあります。調査業が取り扱う情報の多くは、個人情報であり、今後の調査業活動を考えるにあたっては、個人情報の保護の視点をもつことが重要となっています。調査の過程で、情報を収集する場合は、適正な手法により収集するとともに、いったん収集された情報が漏洩したりしないよう、適正に管理する必要があります。また、個人情報には、センシティブ情報と言われる情報があります。たとえば、思想、信仰、信条や病気・健康などの心身の状況に関する基本的な個人情報は、個人の内面に深く関わる情報です。さらに、民族、国籍、本籍などの情報は、社会的差別の原因となるおそれがある個人情報です。これらについては、個人の権利利益を侵害する危険性が高く、とくに慎重に取り扱う必要があります。
(6)報 告内容の正確性の確保依頼者に対して、誤った情報や不正確な情報が報告されることで、調査対象者の人権や利益を侵害するおそれがあります。また、いったん発生した人権侵害を救済することは大変困難です。したがって、調査業者は、虚偽の報告はもちろん、十分な根拠のない報告などは行ってはならず、報告内容の正確性の確保に最善を尽くす必要があります。
6 人権意識向上への取り組み
(1)調 査業は、人権問題に密接に関わっていることを認識し、受件、調査、報告の全過程を通じて、調査対象者の人権の尊重に配慮するとともに、自らの人権意識の向上に努める。
(2)こ のガイドラインに示す人権尊重の精神を遵守した調査活動が実施されるよう、従業者に対しても適正な指導及び監督に努める。
【趣 旨】調査業は、他人の人権にもっとも密接に関わっている業務です。調査活動を通じて、個人の利益を侵害する危険性と絶えず隣合わせているとともに、具体的な依頼案件を通じ、社会の差別意識を実感させられる場面に遭遇することも多々あります。調査業者は、調査のプロフェッショナルであるとともに、社会の人権意識を変えていくキーパーソンでもあります。調査業が、業界として発展していくため、高度な人権感覚を経営者、従業者ともに身につけ、業を通じ、社会の人権意識の向上に果たす能動的な役割が期待されています。
【説 明】
(1)人 権意識の向上調査業が、人権問題に密接に関わっている業種であることを認識し、受件、調査、報告の全過程を通じて、人権を侵害しないよう留意しなければなりません。また、個人情報の保護をはじめとした個人の人権の尊重について、常に意識するなど、企業のグローバル・スタンダードとなりつつある「人権」に配慮した経営に努めていきます。
(2)従 業者に対する指導・監督そのためには、経営者だけでなく、人権が尊重された調査活動が常に実施されるよう、従業者に対して必要な教育、指導及び監督に努めることが必要となります。こうした努力を積み重ねていくことが、信頼ある業として、長期的に見れば、業界の発展につながると考えます。
業界全体の発展と社会への貢献条例を遵守し、自ら適正な調査活動を行うとともに、行政との連携のもとに、人権尊重を基本とする健全な業者の育成に努めるなど、信頼される調査業の構築に努め、人権が尊重される社会の実現に向けて貢献する調査業をめざす。
【趣 旨】業界に対する信頼度を向上させていくためには、業界の自主努力が最も有効です。
【説 明】調査を自主規制していくことは、短期的には、営業活動領域を狭めてしまうように思われがちですが、長期的に見ると、意識の高い業者が峻別され、業者のイメージ、社会的地位が向上することにつながります。また、そのためにも、より多くの業者がそのことについて理解をし、進めることが必要となってきます。情報化や企業や官公庁の情報公開が伸展するなかで、依頼者に対し、真に必要で有効な情報を提供するために、その専門家としての調査業の果たす役割は、一層広がることが予想されます。これまでの調査業の蓄積を生かし、すべての人の人権が確立された社会を実現するために貢献するとともに、これからの変革の時代を経て、調査業も大きく飛躍していきたいと考えます。以上-
≪調査業者のガイドライン捕捉説明≫当ガイドラインが作成されてから既に13年の歳月が経過しました。その後、探偵業法の施行をはじめとし、個人情報保護法、消費者保護法、住民基本台帳法等の施行、そしてIT並びに探偵調査機材の急激な進歩により探偵業界を取り巻く環境は大きく変化しました。時代が変わつても調査業者のガイドラインの目的、基本的事項は、大きく変化するものでは有りませんが、インターネットの普及により各社の広告活動はネット広告が主流となりました。この広告活動において、調査内容を伝える文言内容によっては、興信所口探偵会社による公簿(住民票や戸籍謄本等)の不正取得を暗に想像させ、誤解を招くケースがあります。したがいまして、各社におかれましては、ネット広告をはじめ各種広告媒体での使用文言には、十分なご注意とご配慮をお願い致します。
【不適切文言使用事例と対応策】
1.各種公簿の取得(不正な取得行為)
2.結婚調査において
1)相手方の国籍、本籍等、家族構成等の調査
2〕相手の釣書〔経歴書)の内容確認
3)釣書の確認調査4)身上書の確認調査
5)家系調査3.Ellれさせ屋/復縁屋4.そofE
1.違法行為であり論外
2.結婚調査自体は、何等問題はありませんが1)〜5}の個別調査内容文言は、ガイドライン4-1、 5-4,5-5に1日朧す
●疑念をいだかせる文言であり、表現の変更又は削除が必要です。
3.この業態は、本来調査業者の業務内容にはなく、公序良俗に反する活動であり、使用はできません。
バナースペース
一般社団法人 大阪府調査業協会
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3-1-16
TEL 06-6867-7657
FAX 06-6867-7658
E-mail : info@daichokyo.or.jp
URL : https://daichokyo.or.jp
[協会概要詳細 ]
[業務内容詳細]
![]() 入会申込書
入会申込書